新しい働き方に向けて①
- 吉岡 俊史
- 1月20日
- 読了時間: 3分
オフィスワークに対してテレワークという言葉が出てきてから、実に40年以上経過しているそうです。
テレワークがあたかもコロナ禍で始まった印象がありますが、コロナ禍で一般的に広がっただけで、最初に始まったのは1980年代だそうです。
ネット記事からの情報になりますが、日本でテレワークを始めたのは電気メーカーで、都心の地価高騰に合わせて都心から離れた場所でも仕事ができるように考えられたのがきっかけだそうです。
テレワークはごくごく一部の企業、職種に限られた特殊な働き方だったのだと思います。
海外に目を向けると、テレワークという働き方は、日本よりさらに10年早く1970年代からあったそうで、理由は地価高騰ではなく、地震などの災害からのリスク回避であったそうで「さすが・・コストだけ見た日本より進化している!」と感じました。
まるでコロナのような感染症や特に自然災害を当時から予見し、一極に集まって仕事をするリスクを分散して、事業継続をめざしたのだろうと思います。現在機能しきれているかは別としても、早くからリスクに備える考えがあったことには驚きます。
さて、そのようにテレワークはいまいま登場した働き方ではないのですが、現在はオフィスワークかテレワークかの選択ではなく、両方が併存するハイブリッドワークが多くの企業でも大小問わず広がりつつあります。
緊急時だけテレワークを認める会社、特定の社員(育児や病気等)が利用できる会社や、社員が自分で働き方を選択できる会社などハイブリッドワークのメリットも大いにありそうです。
それを利用して障がいのある方も働く機会を得やすくなってはいます。事実、障がい者雇用の求人の中には、在宅勤務の文字が少しずつ増えています。
ただ、良く見ると、在宅で勤務できるがゆえに、業務のルール、拘束性、成果第一といった管理色が強く出ていて、堅苦しい働き方になっているようにも見えます。
上司が直接仕事の様子を見れないので、何をしているかわからない、だから縛りを厳しくする・・・報告や成果のハードルをあげる・・という印象です。
働き方は自分に合わせられても業務自体がかえって難しくなっていて、障がい者雇用にも向かない場合もあるようです。
それであったら出社した方が働きやすいかもしれない・・・と感じる時もあります。
日本の仕事文化が、個々に異なる事情や条件を持つ在宅勤務者に慣れていないため、在宅勤務に向いている仕事の与え方や管理の仕方に追い付けていない企業もあるのだと思います。
ABWと言われていますが、場所だけではなく時間も自由に選べる働き方があります、過去にはフレックスタイムなどと呼ばれていたものに加え、場所も自由に選ぶというものです。
心身に障がいや病気のある方は、体調に合わせて出勤か休むか、という二肢であったところ、ABWなどが進展すれば、今まで会社を欠勤するしかなかったところを仕事時間に充てられるかもしれないのです。
しかし上記に触れましたとおり、それには本来の仕事の与え方、従業員の評価やコミュニケーションの方法など、全体に渡る文化や考え方がもっと多くの企業で変わってくることが必要になるのではないでしょうか。
障がい者雇用の成否と責任を、働く側だけに求める段階は、過去のものなのだと思います。
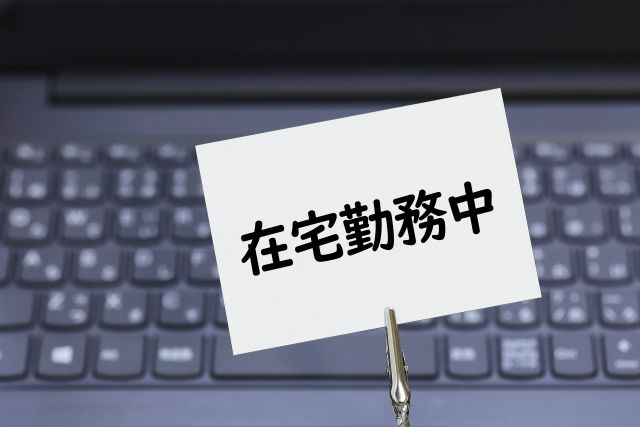

Comments